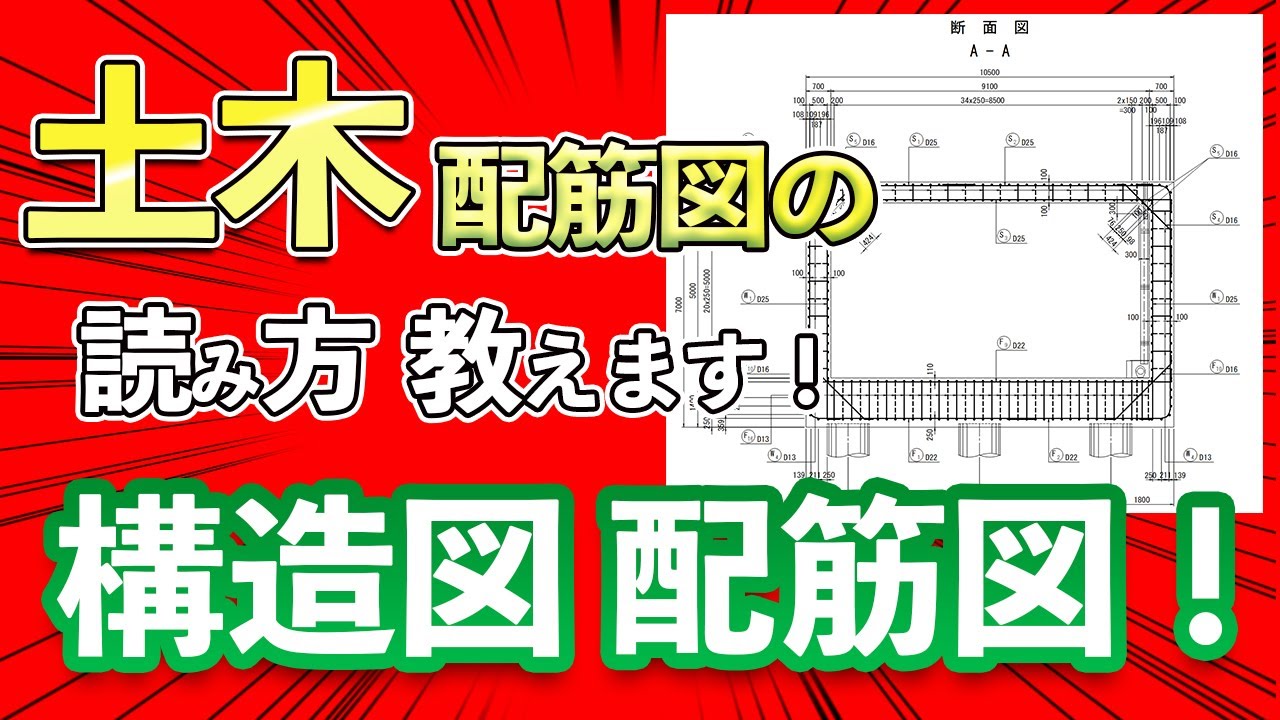こんにちは! ジョウ所長です!
今回は、土木の現場で第一歩を踏み出した新人さん向けに、「配筋図って何? どうやって読むの?」という疑問について、やさしく解説していきますね。 現場で必ず出会う重要な図面なので、しっかり基本を押さえていきましょう!
1. そもそも配筋図って何?
まず最初に知っておくべきことですね。
配筋図(はいきんず)とは、コンクリート構造物の中に入れる「骨」となる鉄筋について、「どこに」「どんな種類の鉄筋を」「どのように配置するか」を示した、いわば鉄筋の設計図・組立図です。
例えば、水の通り道や通路などに使われる箱型のコンクリート構造物「ボックスカルバート」。 この構造物を真横から見たり、上から見たり、断面を見たりしながら、どこにどんな鉄筋が、どんな間隔で入っているかが細かく描かれている。それが配筋図です。
最初はまるで「暗号文」のように見えても、まったく心配いりません!誰でも最初はそうです。 毎日少しずつでも見慣れていけば、自然と「あ、これはアレのことか!」と理解できるようになりますから、焦らずいきましょう!
2. 配筋図に書いてあること
じゃあ、具体的に配筋図にはどんな情報が書かれているんでしょうか? 主なものを紹介します。
▶️ 1. 鉄筋の太さ、本数、間隔(ピッチ)
- 例)
D25→ 直径25mmの鉄筋(異形棒鋼)を使う@250またはピッチ250→ 250mmの間隔で配置する
このように、「どんな太さ(種類)の鉄筋を、どれぐらいの間隔(ピッチ)で、何本並べるか」という、配置の基本情報が示されています。
▶️ 2. 鉄筋の継ぎ方(継手:つぎて)
鉄筋は工場で作られる長さ(定尺)が決まっているので、長い距離が必要な場合は現場で「継ぎ足す」必要があります。この継ぎ方を「継手(つぎて)」と言います。配筋図には、この継ぎ方のルールも指示されています。
- 例)
- 「重ね長さ
790mm以上」 → 鉄筋同士を重ね合わせる長さは790mm以上にすること - 「交互に配置」 → 継手の位置が同じ場所に集中しないように、位置をずらして配置すること(弱点を作らないためです!)
- 「重ね長さ
鉄筋を重ねてつなぐ「重ね継手」が一般的ですが、その重ねる長さや、継手の位置に関する重要な指示が書かれています。
▶️ 3. かぶり厚さ(コンクリート表面と鉄筋の距離)
「かぶり」または「かぶり厚さ」とは、鉄筋の表面から、それを覆うコンクリートの表面までの最短距離のことです。
- 例)
かぶり 100mm→ コンクリート表面から一番近くにある鉄筋の表面まで、100mmの厚みを確保すること
この「かぶり厚さ」がしっかり確保されていることで、中の鉄筋が錆びたり腐食したりするのを防ぎ、構造物全体の耐久性を高める大切な役割を果たします。
▶️ 4. 鉄筋の加工形状
鉄筋は、現場に納入されるときは基本的にまっすぐな棒状です。でも、構造物の形に合わせて、現場や加工工場で図面通りに曲げたり、切断したりする必要があります。 配筋図には、どの鉄筋をどんな形に、どんな寸法で加工するかの詳細な情報(加工図、加工寸法)が、鉄筋一本一本について書かれているわけです。
▶️ 5. 鉄筋集計表(材料表・重量表)
配筋図の最後の方には、多くの場合、その構造物で使う鉄筋の種類ごとの本数や長さ、重さなどがまとめられた一覧表(集計表)が載っています。
- 各鉄筋マーク(D13, D16, D25など)ごとの総本数や総延長
- 鉄筋の総重量
などが一覧でわかるようになっています。 最初は数字が多くて難しく感じるかもしれませんが、「この構造物には、これくらいの鉄筋が使われているんだな」と全体像を把握するのに役立ちます。これも少しずつ見慣れていきましょう!
3. 現場での配筋チェック!
図面が読めるようになったら、次は現場での確認(配筋検査)です! 実際に鉄筋が組まれたら、ちゃんと配筋図通りにできているか、以下の点などをチェックします。
- 鉄筋の種類や太さは合っているか?
- 本数は足りているか? 間違って多くないか?
- ピッチ(間隔)はメジャーなどで測って、図面の指示通りか?
- 継手の重ね長さは規定以上あるか? 交互配置になっているか?
- かぶり厚さは専用の道具(スケールなど)で計測したり、スペーサー(鉄筋と型枠の間に置く部材)が正しく設置されたりしているか?
【よくあるミス】
- ピッチ(間隔)の間違い
- かぶり厚さの不足
- 継手長さの不足
こうした間違いや不備は、コンクリートを打設した後では修正が非常に困難で、構造物の強度や耐久性に影響する大きなトラブルになりかねません。 そのためにも、配筋図をしっかり読み解き、正しくチェックできる力を身につけていきましょう!
4. まとめ:最初は配筋図が「わからん!」で大丈夫
ここまで読んで、「やっぱり難しそう…」と感じたかもしれません。でも、安心してください! 最初は、配筋図を見てもチンプンカンプンで当たり前!
けれど、現場で毎日こつこつ図面を見て、実際の鉄筋と見比べているうちに、「あれ? この記号、前も見たな」「この線は、あの鉄筋のことか!」と、点と線がつながる日が必ず来ます。
最初の一歩は「読めない…」と怖がらずに、とにかく図面に触れること! 先輩に聞いたり、このブログのような解説を参考にしたりしながら、たくさん見て、慣れていくことが一番の近道です。
本日の話が、土木技術者としてのあなたの素晴らしいキャリアの、最初の一歩の役に立てば、すごく嬉しいです!